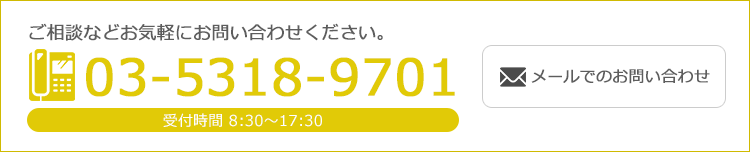投稿者:落合智貴
アベノミクスも4年目に入りマイナス金利も実施されましたが、景気の回復を大きく実感できるには至りませんでした。横浜のマンションが傾く、いわゆる「杭打ち問題」が発覚したのもこの年です。
一方インバウンドが年間2000万人近くになり東京五輪に向けた宿泊施設の供給にも限界が見られ、民泊の法制度が検討されたり、ホテルの建設計画が進められるなど、観光立国への転換が進められたのもこの頃です。
かつて日本の高度経済成長は工業製品を輸出することで支えられていました。
しかし工場の海外移転が進む中で、日本経済を支える柱の一つが「観光」になったことを感じました。
当社は組織の在り方を一歩踏み出す年になりました。
社員の中間層が40代になり、20代の若手が成長していく中で、初めて部長・課長のポストを新設しました。
ベテランにやりがいと責任を感じられる組織。
若手にやる気と希望を感じられる組織。
そんな組織に少しでも近づけていきたいとの思いでした。
また社員の投票で会社のイメージカラーを決めました。
約3か月を費やし、投票を重ねて皆で選んだカラーが紫と黄色の組み合わせです。
色が決まったのち当社が古くから使っているロゴマークに色を付けて立体的にしたものを作成し、ホームページやトラックの後ろに使っています。
「スムーズな設備工事現場をお手伝いします」とのコーポレートメッセージと共に、皆で決めたカラーが多くの人の目に留まり、企業イメージのアップにつなげたい。
そんな思いが詰まっています。