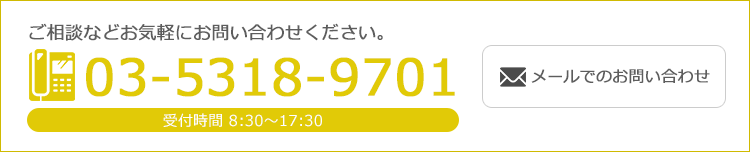投稿者:落合智貴
先日の台風19号では各地に洪水など大きな被害が出ました。
千曲川や阿武隈川など、多くの河川で堤防が決壊するなど氾濫しました。
この台風で亡くなった方は福島県で30人、宮城県で16人、神奈川県で14人などと報道されています。洪水によって建物が水没したり流されたり、土砂崩れも多く発生しました。電柱が倒れることによる停電や、高層マンションなどでは電気室が水没することによる停電もありました。
温暖化の影響によって今後同規模の台風が頻発することも想定しなければならなくなりました。
今後の課題としては、避難のあり方などソフト面が一つ。ダムや貯水施設の建設や、堤防の補修などハード面の整備が二つ目となります。しかしハード面は相当の時間とお金がかかります。
 【 台 風 1 9 号 に よ り 千 曲 川 が 氾 濫 】
【 台 風 1 9 号 に よ り 千 曲 川 が 氾 濫 】
そもそも「水」はありがたい存在で、人類の文明はメソポタミア文明やインダス文明など川の近くから発展がはじまりました。農業に水が必要なのはもちろん、生活用水を確保する意味でも川の近くが都合が良かったためと学校で習いました。
日本で上下水道が広く普及するようになったのは昭和の高度経済成長の時代です。
つい数十年前までは日本でも井戸水を使うのが当たり前でした。
当社の仕事も水道インフラの発展に寄与していると自負していますが、これだけ豊かになり、技術が発展しても風水害は防げないんですね。
電気が水に弱いというのも都市化の弱点と言えるかもしれません。
水は生活に欠かせないと共に怖さも併せ持つ存在です。
今回の台風で「水」の存在は有難いと共に怖い存在であることをあらためて感じました。