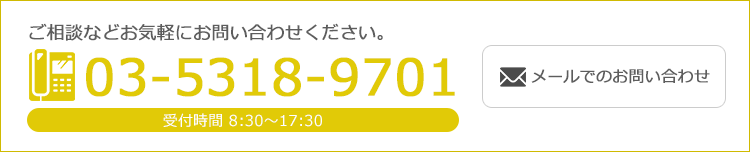投稿者:落合智貴
ロルフ・ドベリ著「Think clearly」を読みました。生きていると嫌なことも多いですし、自分が幸福でないと感じている人も多いのではないでしょうか。この本では複雑な世界をどう生き抜いていくかを“思考の道具箱”として52個示し、よい人生を送るために日々どう考えていけばよいかを教えてくれます。私が特に共感できた項目をご紹介します。

1、考えるより、行動しよう
文章を書くときに、アイデアは「考えているとき」ではなく「書いている最中」に浮かぶものである。長く思い悩んで「思考の飽和点」に達したらこれ以上考えても意味がない。人生において自分が何を求めているかを知るには、何かを始めてみるのが一番である。
12、本音を出しすぎないようにしよう
「オープンな人」は親密で心地よく付き合いやすいが、極端にオープンな場合は周囲に不快感を与えてしまう。自分の心の内を語っても尊敬は得られない。口にした約束を果たすからこそ尊敬される。アイゼンハワーは「二番目の人格」を作り上げた。
13、ものごとを全体的にとらえよう
特定の事について集中して考えている間はそれが人生の重要な要素のように思えても、実際にあなたが思うほど重要なことでもなんでもない。マイアミビーチに住んだり、億万長者になったりすることで幸福度がアップするとは限らない。3歳の子供が目の前のおもちゃを取り上げられて泣き叫ぶようにではなく、広角レンズを通して自分の人生を眺めよう。
16、自分の向き不向きの境目をはっきりさせよう
ウォーレン・バフェットは「能力の輪」と表現しており、大事なのはその輪の境界がどこにあるかを見極めることである。魅力的な仕事であっても「能力の輪」の範囲外の仕事だったら断るのが良い。ひとつでも素晴らしい能力があれば、欠点がいくつあろうと帳消しになる。
34、解決よりも、予防をしよう
経営破綻しかけた企業の再建はメディアにもてはやされるものである。しかしもっと高く評価されるべきは企業再生が必要な状況に陥ることを未然に防いでいるマネージャーの方である。個人においてもあなたの人生で起こりうる「大きなリスク」について集中して考える時間をもつべきである。
39、「心の引き算」をしよう
今あなたは幸せを感じているか?目を閉じて、今の状況から右手を失い、左手を失い、視力を失い、子供を事故で失うことを想像してほしい。今の状況がとても幸せに感じられるのではないか。
52、内なる成功を目指そう
アメリカのバスケットボール選手ウッデンは「成功とは、最高の自分になるために全力を尽くした後に得られる心の平和の事だ」と述べている。物質的な成功より内面の充実の方が大切である。