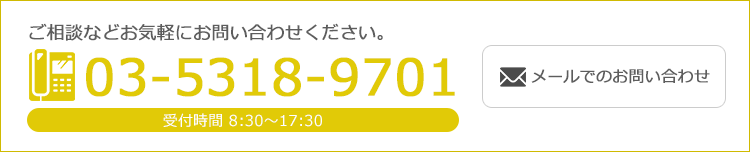投稿者:落合智貴
第二次世界大戦後の世界は米ソ冷戦状態が永く続いていました。日本はその間急速な経済成長により戦後復興を果たし、世界第二位のGDPまで上り詰めました。その後ベルリンの壁崩壊やソ連崩壊によってポスト冷戦時代へと続きました。ポスト冷戦時代の日本はバブルが崩壊し、30年の長きにわたって低成長を続けているうちにGDPで中国に抜かれ、一人当たりGDPも2022年現在で世界30位に甘んじています。
「新冷戦の勝者になるのは日本(中島精也著)」では新冷戦において日本が大復活を遂げる条件が整っていると述べています。

新冷戦とは2017年の習近平国家主席の中国共産党大会のスピーチを皮切りに、世界覇権を狙う中国とそれを阻止すべく反撃をする米国の対立を軸として、権威主義と民主主義が戦う構図であり、ロシアのウクライナ侵攻はそれを象徴するものです。
第8章では「新冷戦は日本大復活の時代」と題し、日本復活の理由を説明しています。
ポスト冷戦時代では、冷戦終結とバブル崩壊が重なり、円高によって国内製造業がどんどん海外にシフトしていき、国内経済が空洞化していきました。その後金融緩和によって多少の円安に戻りましたが、日本の供給力がすでに落ちてしまっていたため、円安→輸出増加→生産増加→労働需給の逼迫→賃金上昇→インフレ→消費拡大→設備投資拡大→成長率の上昇 といった好循環のメカニズムが働かなかったというのです。
しかし昨今の大幅な円安によって製造業の国内回帰が徐々に進んでいます。安倍首相の“地球儀を俯瞰する外交”の成果として、台湾TSMCの半導体工場を熊本に誘致したことは国内設備投資の呼び水になると予想されています。アベノミクスによって株価や不動産価格がバブル期並みまで回復し、日本を苦しめてきたバランスシート悪化・円高・産業空洞化は過去のものとなった。日本が国際競争力をもつ、ips細胞・半導体製造技術・医療機器・工作機械などのポテンシャルは高い。ポスト冷戦期に日本に不利だった条件が新冷戦期においてオセロゲームのように日本有利になっていくだろうとのことです。
日本の復活に期待したいと思います。