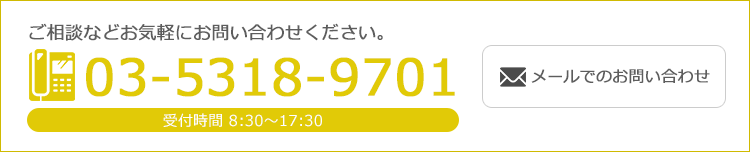投稿者:落合智貴
ご承知の通り、野球のワールドベースボールクラシック(WBC)2023で日本がアメリカを決勝で破り優勝しました。日本中が沸いていますね。
今までの日本は体格差で劣るアメリカに対して、きめ細かい小技で勝負するスモールベースボールのイメージが強かったです。しかし今回のチームは選手が大型化し、パワーでも負けないチームで臨むことが出来ました。
メンタル面でもチーム全体が前向きな雰囲気を作り出し、チャンスやピンチでもプレシャーに押しつぶされることなく自分たちの力を出し切ることが出来たと思います。
今回の勝因はなんといっても栗山監督の一貫したチームコンセプト作りだったと思います。
ベテランとして皆が尊敬するダルビッシュ投手、世界が誇るNo.1プレーヤーの二刀流大谷選手、日本では無名だった日系メジャーリーガーのヌートバー外野手など、自分がこのチームいる意義をよく理解した人たちを集めたチーム編成だったと思います。

そして選手起用に関しても、選手を信じ切って任せることを通しました。不振だった村上選手が、準決勝のメキシコ戦で1点差で負けていた9回裏0死1,2塁の場面で登場。バントをさせてもおかしくない場面でも村上を信じて打たせ、逆転サヨナラ二塁打を導いたのはこの大会最大の決断だったと思います。
あまり目立ちませんが、今回のヘッドコーチを務めた白井一幸氏は元日本ハムの選手、二軍監督などで活躍した方で、若手育成に関する著書もあり講演活動も行っています。選手には手取り足取り教えるのではなく、自分で考えさせ、自分の意志で努力をさせるコーチングの理論をしっかりと確立している方です。前提としては選手をリスペクトすることからスタートするのが最近のコーチング理論だと思います。
野球におけるチーム作りと会社におけるチーム作りは共通するものが多いと思います。
今回のWBCから学べることは多いかもしれませんね。

【白井一幸ヘッドコーチ】